[インタビュー]「あえて削ぎ落とすことで“話題にしたくなる”」PR観点でOOH(屋外広告)を考えるプランナーの仕事
2025.12.13 / Special

―2024年6月、本格化していく就職活動というタイミングに向けて、就活支援サービス「OfferBox」を手掛けるi-plugは、「みにみにぴにぴに」という、一見理解が難しいワードを全面に押し出した「口角が上がる広告」を渋谷駅構内ほか大学の周辺駅などで展開。
広告でありながら多くのメディアに取り上げられた本企画のプランニングを担当したコミュニケーションデザイン局の藤田さんに、PRの仕掛けや設計について伺いました。本企画は2025年4月1日に発表された「第9回JAAA若手大賞」でもファイナリストに入選しました!昨年の「視線が上がる広告」に続き、就活生が前向きな気持ちになってもらうことを目指した第二弾の企画となります。

―どのようにして生まれた企画なのか教えてください。
まず、「OfferBox」がターゲットとする就職活動の環境は年々変わっていて、例えば選考の早期化や、コロナ禍の影響によるガクチカ不足、採用形式の多様化など就職活動自体の変化が一層激化している状況下で、学生は就職活動に対して不安や緊張を感じている傾向にあります。そんななか、少しでも学生が前向きになれるきっかけを与えられないかと生まれたのが今回の企画です。
当時のプレスリリース:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000041771.html
―クライアントの与件と、どのような提案を実施されたのか教えてください。
クライアントの与件としては、「就活生に寄り添うサービスだと学生たちに認知されたい。就活支援サービスとして独自のポジションを確立したい。」という2点でした。そこで、就活が本格化するタイミングでOOHでブランドメッセージを打ち出すこと、それもただ「がんばれ」のようなメッセージを一方的に投げかけるのではなく、それを「体感」のある形で受け取ってほしかった。そこで「声に出す」ことでのポジティブ効果に目をつけ「口角が上がる広告」を作りたいと考えました。実際に関西大学の熊谷学而准教授監修のもと、声に出したとき最も前向きになる言葉として新たに生み出したのが、「みにみにぴにぴに」です。
媒体はOOHなので、実際に目の前を通る学生は限られます。なので、SNS、主にXで拡散されることを前提にクリエイティブにすること。それが話題化することでメディアにも伝播し、取材につながるという流れを作り出したいという狙いがありました。

ーOOHで話題化するものはしばしばあると思うのですが、今回のPR観点を活かしたOOHだからこその違いはなんでしょうか?
まず、1つに「広告を起点としてPR的にも話題化させるための情報設計」が言えると思います。
SNS上での「何だこれ?」という声や、謎の広告という違和感こそメディアの企画のフックになると考え、ぱっと見た感じの違和感や、目に留まるよう印象づける広告にするよう意識しました。
さらに、その先のメディアの記事に必要なことから逆算し様々なコンテンツを用意した上で就活シーズンというタイミング性なども考えて発信を設計したことで、実際にメディアからも多くの取材をいただきました。
また、クリエイティブがメディアに取り上げられて記事に出たときのタイトルや、プレスリリースにした時のタイトルを考えながら企画をつくって行くことも重要です。今回は「口角が上がる広告」という言葉を考え、そのために何が必要か考えていきました。何が面白いポイントなのか、第三者に対して言語化して伝わるか試してみることも効果的かもしれません。
私自身もそうですが、プラチナムではメディアプロモート経験のあるプランナーが多いので、メディア起点での発想を得意としている点は特徴だと思います。
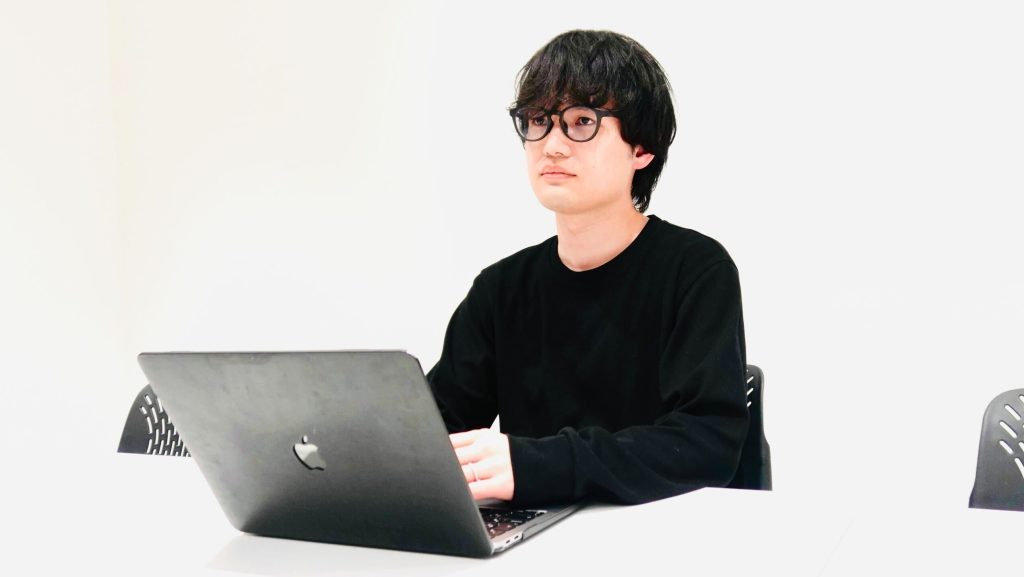
もう1つは「取材前提であるからこそできた斬新なクリエイティブ」です。
「広告施策」と考えて実施すると、メッセージの発信のみで完結してしまうかもしれません。一方で、取材されることが前提にあるからこそ、「みにみにぴにぴに」のように、言いたいことはたくさんあるものの余計なことは削ぎ落したクリエイティブに挑戦できます。 PR発想で考えることで、広告も新しいアプローチを仕掛けられたり、さらに広告への投資対効果も最大化していけると考えています。
―今後どのようなプランナーを目指していきたいですか?
「おもしろい」にチャレンジし続けていくプランナーです。そもそも、企業からのただのメッセージには生活者は興味ないだろうと思ってます。コミュニケーションに携わる仕事として、思わず見てしまうとか、注目してしまうとか、そういう企画をPR視点でつくっていきたいです。
そしてその先に、実際にブランドが好きになるとか、モノが売れるとか。マーケティングのインパクトも狙っていきたいと思っています。
■藤田さんが手掛けた広告を活かしたPR事例
「おいでまい!さぬきプロジェクト」
2025年1月より創業25年目を機に始動した「おいでまい!さぬきプロジェクト」を担当。その一環として、同年2月に、高松琴平電気鉄道株式会社が運営することでん長尾線林道駅の副駅名を「はなまるうどん駅」に変更。創業店舗の最寄駅である林道駅のネーミングライツ施策に、多くの地元メディアが取材。本企画は、はなまるうどんとして地元香川を盛り上げたいという思いを通じて「乗ってみたくなる」まで落とし込むことを重視し、林道駅の壁面に巨大うどんパネルを掲示。
駅名の由来を伝える言葉と、力強く伸びる讃岐うどんの写真が特徴。コラボ車両内のとある車窓には、はなまるどんぶりのステッカーを掲示しており、「ことでん林道駅 はなまるうどん駅」を通過する際にホームに設置された巨大うどんパネルと重なることで、「うどん箸上げ」ができる仕掛けとなっており、運が良ければ、巨大うどんと箸がぴったり重なるクリエイティブを見ることができる。
プレスリリース:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000388.000019432.html

「PRINGLESCAN(プリングルズスキャン)プロジェクト」
ポテトチップスのブランド「プリングルズ」は、2024年9月に、内容量はそのままに、パッケージのサイズを15mm短くコンパクトにする商品改定を実施。
新ショート缶をX線で透過し、プリングルズの中身のポテトチップスが丸見えになった「ポテチのレントゲン広告」を東京メトロ新宿駅構内に掲出。パッケージがコンパクトになると、どうしても「中身も少なくなったのではないか?」と考えられてしまいがちだが、量は変わらないというポイントをよりポップに、かつポジティブに知ってほしいという企画。
見る方向によってビジュアルが変わる特殊加工を施しており、片方から見ると通常のプリングルズのショート缶が、もう片方から見るとX 線にて検証された“透け透けプリングルズ“が現れるという、見る角度によって全く異なるビジュアルを楽しめる広告に。
プレスリリース:
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000012584.html
